
「アズマダチ」の名の由来

散居村の家屋を見て回ると、ある共通点があることに気付きます。それは家の正面(正面玄関)が東を向いていることです。
東を向いている理由は、砺波平野の冬の季節風は主に南西から吹きます。そのため屋敷林は南西側を特に厚く覆っており、朝日の上がる方向でもあり、入口は屋敷林の少ない東側に配置しています。家が東(アズマ)側を向いていること、武家(アズマ)風屋敷をまねたことからとも言われています。
「屋敷林」と「アズマダチ」をじっくり見学

伝統館は、大正時代〜昭和初期の「アズマダチ」を昭和30年代の雰囲気そのままで移築した建物です。「アズマダチ」正面の白壁、「ワクノウチ」の構造、「ゲンカ」の土間、昔ながらの「ナガシ」など昭和世代にとっては懐かしさを感じる雰囲気です。今では少なくなった建物で、昔の暮らしの様子をじっくりと見学いただけます。
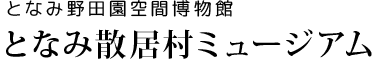











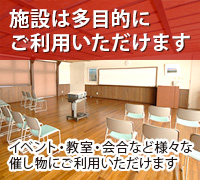
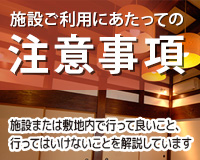






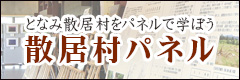





散居村の代表的な家屋様式のひとつ「アズマダチ」
見学料:無料
散居村は、個々の家が点在しているため、冬の季節風、夏の暑い日差しなどを防ぐため屋敷林(カイニョ)が植えられています。
その屋敷林の中にある家屋は、江戸時代の砺波地方では「寄棟造」の茅葺き屋根で、平均的には20〜30坪の建物でした。
明治時代頃から富裕層の農民の中には、大きな切妻屋根に葺き替えて妻側に家の玄関を設けて妻面の束や貫を意匠的に組んでその間を白壁にぬる「アズマダチ」と呼ばれる見事な造形の建物に改築しました。